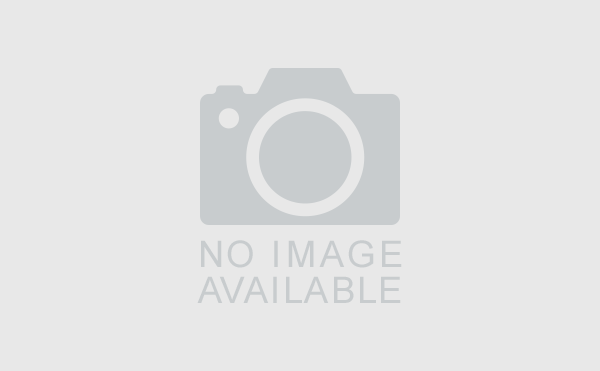本の紹介 47
かねこカウンセリングオフィスの金子です。
本日の本の紹介はこちら!!
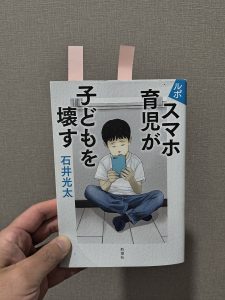
「スマホを育児が子どもを壊す」石井光太、新潮社、2024.
付箋がついたままですみません(;´∀`)
一言で言えば、
とても興味深く、スマホの使い方を改めて見直すいいきっかけとなりました!
子どもにスマホを持たす前に、是非、親として読んでおきたい一冊です!
これまた、たくさん皆様にご紹介したい箇所があったのですが、多すぎるので、後半部分の大学教授の言葉を引用させて頂きます。
P238
元中学教員で、現在は兵庫県立大学に勤める竹内和雄教授は話す。
「コロナ禍を経て、子どもたちのネット接続時間は一段と長くなり
それを防ぐためにはルール化が必要ですが、大人が一方的に決めて
私も同感です。
しかしながら、子どもと親の関係性によっては、コミュニケーションが取れないことや思春期に入り、複雑かつ不安定な情緒となっている子どもと冷静な対話が出来る親は多くはないとも思います。
実際に、子どものスマホの使い方や制限をどうしたらよいか?といった旨の保護者からのご相談をこれまで数えきれないほど、してきました。
絶対的な正解や魔法のような特効薬はないですが、基本姿勢としましては、
「親子のコミュニケーション」の重要性をお伝えすることが多いです。
換言すれば「雑談の大切さ」とも言えるでしょう。
やや抽象的にはなりますが、何気ない、他愛ない会話の中に、ぽろっと本音が出たりするものです。
突然、子どもの核心をついた質問をしても、返答に困ることや、時に「うるさいな!」とシャッターを閉められてしまうかも知れません。
そうではなく、お夕飯の時に「今日のお肉はおいしいね」やテレビを見ながら「このお店に行ってみたいね」といった何気ない会話の積み重ねをしていくこと。それが親子のより良いコミュニケーションとなっていくものと思います。
現在、お子さんのスマホやタブレットの使い方や制限方法でお悩みな保護者の方がいらっしゃいましたら、ちょっとこの点を意識してお子さんと接してみて頂ければ幸いです。
ではでは。