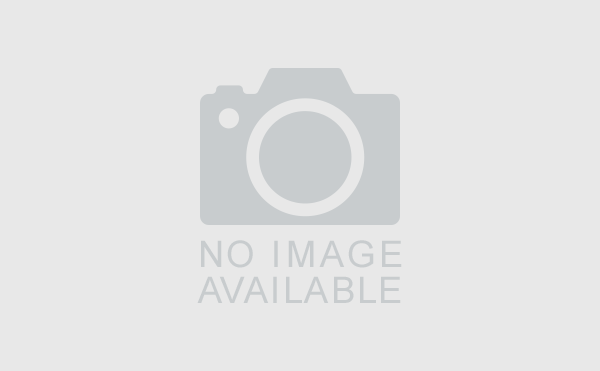本の紹介 39
かねこカウンセリングオフィスの金子です。
今日は本当に寒いですね・・・⛄
数日前には雪予報でしたが、冷たい雨になりましたね。
中学受験が2/1~始まっていますが、受験生の皆さん、自分自身の実力を十分に発揮できることを祈っています!
前置きが長くなりましたが、
お正月休みに読んだ本 パート2!笑です。
「発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと」
“周囲とうまくやっていく力”の育み方、宮尾益知監修、大和出版、2024.
以下↓引用です。
P95 おわりに
どんな親御さんもみんな真剣な面持ちでクリニックにやってきます。「こうしたらどうですか」という提案を素直に受け入れ、すぐに実行してくださる家庭では、時間はかかりますが、着実に改善していきます。
なかなかうまくいかないのは、親御さんが「やっています。でも、忙しくてそんなことまでできません」と言ってしまう場合です。
いまの親御さんは、共働きやシングルのケースもあり、多忙で疲れています。子育てに困難さがともなうなら、なおさらです。
でも、発達障害やギフテッドの子の生きづらさをとり除くには、時間をかけて本人の社会性や情動を育んでいくしかありません。成長をただ待つのではなく、段階をふんで内面から少しでも変えていくことが大切なので。「忙しい」「できない」という自分の視点ではなく、親御さんにこそ、子ども側に立つ他者視線をもってほしいと思います。
いまお子さんは、発達の途上にいます。このタイミングだからこそ、お子さんの状態をよくするために努力できるのです。医師、学校の先生、周囲の人の手助けも得ながら、前向きに取り組んでいきましょう。
はい・・・
私もスクールカウンセラーのカウンセリング場面で、保護者の方々とお会いすることが多くありますが、皆さん、お子さんのことで悩みに悩んで、カウンセリングに来られます。まずは、経緯と現状を真摯に聴き、気持ちを汲み、寄り添いながら話しを進めていきます。
そして、一通り、話しが落ち着いたところで、今現在、保護者の方が出来そうなことを共に探し、提案することがあります(私は、限られたカウンセリング時間の中で、最低1つのお土産(=なんらかの希望や提案)を持って帰って頂くよう、気を付けています)。その提案を次回のカウンセリングまでに実行してくださる保護者のお子さんは、既述の引用にもありましたが、「時間はかかりますが、着実に改善して」いくことが多いです(断定はできませんが・・・)。もちろん、お子さん自身の変化や力によって変化が生じますが、近くにいる保護者の言動の変化も自明のことですが、お子さんの変化に大きな影響を与えます。
俗に言う、「親が変れば、子どもも変わる」ということです。
しかしながら、親ゆえになかなか変われない場合もあります。その点が非常に難しい点かと思いますし、カウンセラーの腕の見せどころと個人的には思っています。
長らく、スクールカウンセラーをやらせて頂いていますが、魔法のような解決方法やこれとった絶対の策はありません。毎回、保護者の方と「小さな変化」を集めていく共同作業の繰り返しが、子どもの変化、そして、問題と呼ばれる事象の解決や解消に近づいていくと思っています。
ではでは。